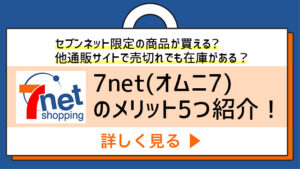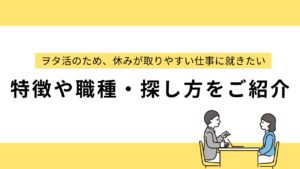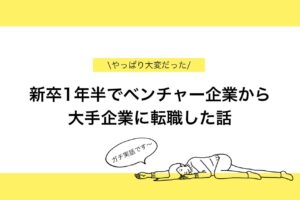宅建試験に受かるには「独学」「通信講座」「学校・予備校」の方法があります。
ちなみに管理人は大学時代法律の授業を4コマくらい取っていたので基礎の基礎は理解した状態からのスタートでした。合格した1年間の勉強時間は400時間くらいです。感覚的には一通り流れを把握してから300時間必要でした。 次に宅建試験に合格するための勉強方法を紹介します。
宅建にするための勉強方法
宅建に合格するには「独学」「通信講座」「学校・予備校」の方法があります。 それぞれにあった方法で合格を目指しましょう。
独学
宅建は独学で合格する方も多くいます。
今の時代はありがたいことにYouTubeで宅建の講義を無料で見ることができますが、正直おすすめはできません。 私は独学で受験していた時、YouTubeの画面にかじりついて全編視聴しました。 しかし次の年に学校の教材で勉強すると、知らなかったこと、勘違いで理解していたことがたくさん出てきました。 あくまで個人的な意見ですがYouTubeの動画では下記理由からおすすめできません。
- 大まかな点のポイントだけをつまんで動画にしているので流れが理解しにくく、齟齬が生じやすい
- もともと頭のいい方が作っているため一般人にはわかりにくい
- 動画の流れで理解した気になってしまう
なので、「不動産業についていて質問できる人がいる」「民法の勉強をしていたのでつまづきやすいの権利関係の解説はいらない」方におすすめです!
独学におすすめのテキスト
2回落ちてるだけあっていろんなテキストを試してます(笑)
1.みんなが欲しかった!宅建士〜シリーズ
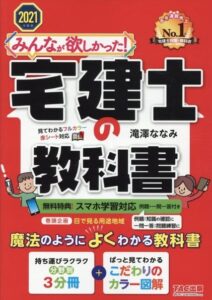
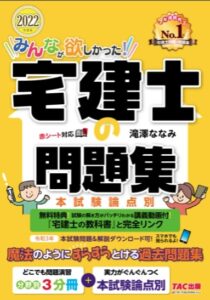 教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
2.LEC 出る順宅建士シリーズ
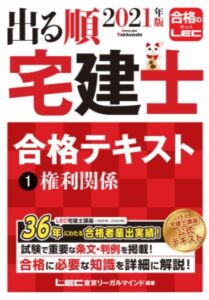
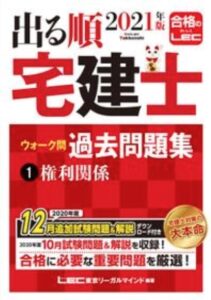 教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
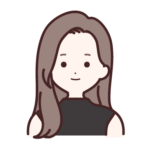
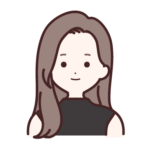
通信講座
正直大手予備校の通信講座以外はおすすめしません。テキストが独特でわかりづらく感じました。私が2回目に勉強したときは独特すぎるテキストについていけず離脱〜
予備校・学校
3回目はついに学校に通いました。(感染症により自宅での映像授業がほとんどでしたが) どうしても受かりたい方はやはり学校がおすすめです。
私は何事も理由と理論がないと暗記できなかったので、理由も一緒に教えてくれる予備校はとてもあっていました。 私はLECに通っていました。やはり法律はLECですね。Twitterの資格アカウントを見ていると行政書士や司法試験もLECを利用している方がダントツで多そうです。 通学でも通信でもいいと思います。 共通しておすすめなのはTwitterの勉強アカウントを作ることです! Twitterで毎日のように勉強報告をしている方のレベルは高いしぼーとTwitterを見てる時に「勉強やらなきゃ」という気持ちになります。何より仲間ができることで途中挫折の確率がぐんと下がります。 すごい人を見て焦燥感や嫉妬で嫌になったりもしますが、辛い気持ちの共有、わかりづらい点、勘違いしていた点の情報共有などメリットがたくさんあります。
おすすめしない勉強法
どうしても言いたいことが2つあります。 一問一答はやりすぎない。 宅建には正解肢だけでなく正解肢以外の解答もチェックする必要があります。 なので一問一答で正解肢だけを覚えていくような勉強はおすすめしません。 もう一つは 模試の復習はやりすぎない。 各会社の模試はとんでもない細かい難しい問題を出してきたりします。しかし宅建に出るような問題は過去問にのっている粒度の問題です。模試すべての問題の復習はしなくてOKです。
まとめ
勉強法をいくつか紹介しましたが、一番大切なのは購入したテキスト、入学した予備校を信じることです。 そして変えないこと。難しい、、わからないと思っても信じて使い続けてください。 難しすぎて自分は本当に受かるのだろうか。。。?と思うこともたくさんありました。 必ずわかるようになります。勉強すれば誰でも合格する資格です。 あなたの合格を祈っています。
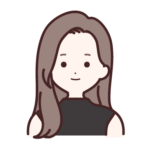
感覚的には一通り流れを把握してから300時間必要でした。 次に宅建試験に合格するための勉強方法を紹介します。
宅建にするための勉強方法
宅建に合格するには「独学」「通信講座」「学校・予備校」の方法があります。 それぞれにあった方法で合格を目指しましょう。
独学
宅建は独学で合格する方も多くいます。
今の時代はありがたいことにYouTubeで宅建の講義を無料で見ることができますが、正直おすすめはできません。 私は独学で受験していた時、YouTubeの画面にかじりついて全編視聴しました。 しかし次の年に学校の教材で勉強すると、知らなかったこと、勘違いで理解していたことがたくさん出てきました。 あくまで個人的な意見ですがYouTubeの動画では下記理由からおすすめできません。
- 大まかな点のポイントだけをつまんで動画にしているので流れが理解しにくく、齟齬が生じやすい
- もともと頭のいい方が作っているため一般人にはわかりにくい
- 動画の流れで理解した気になってしまう
なので、「不動産業についていて質問できる人がいる」「民法の勉強をしていたのでつまづきやすいの権利関係の解説はいらない」方におすすめです!
独学におすすめのテキスト
2回落ちてるだけあっていろんなテキストを試してます(笑)
1.みんなが欲しかった!宅建士〜シリーズ
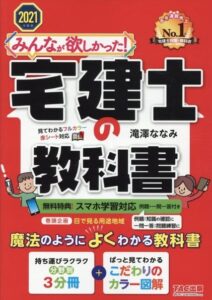
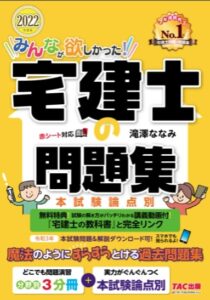 教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
2.LEC 出る順宅建士シリーズ
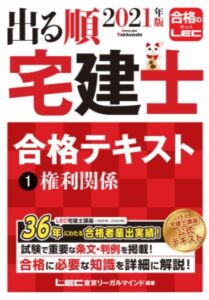
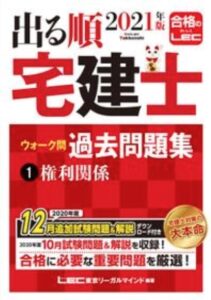 教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
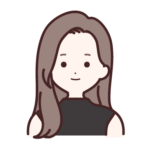
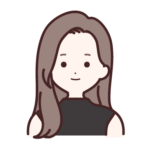
通信講座
正直大手予備校の通信講座以外はおすすめしません。テキストが独特でわかりづらく感じました。私が2回目に勉強したときは独特すぎるテキストについていけず離脱〜
予備校・学校
3回目はついに学校に通いました。(感染症により自宅での映像授業がほとんどでしたが) どうしても受かりたい方はやはり学校がおすすめです。
私は何事も理由と理論がないと暗記できなかったので、理由も一緒に教えてくれる予備校はとてもあっていました。 私はLECに通っていました。やはり法律はLECですね。Twitterの資格アカウントを見ていると行政書士や司法試験もLECを利用している方がダントツで多そうです。 通学でも通信でもいいと思います。 共通しておすすめなのはTwitterの勉強アカウントを作ることです! Twitterで毎日のように勉強報告をしている方のレベルは高いしぼーとTwitterを見てる時に「勉強やらなきゃ」という気持ちになります。何より仲間ができることで途中挫折の確率がぐんと下がります。 すごい人を見て焦燥感や嫉妬で嫌になったりもしますが、辛い気持ちの共有、わかりづらい点、勘違いしていた点の情報共有などメリットがたくさんあります。
おすすめしない勉強法
どうしても言いたいことが2つあります。 一問一答はやりすぎない。 宅建には正解肢だけでなく正解肢以外の解答もチェックする必要があります。 なので一問一答で正解肢だけを覚えていくような勉強はおすすめしません。 もう一つは 模試の復習はやりすぎない。 各会社の模試はとんでもない細かい難しい問題を出してきたりします。しかし宅建に出るような問題は過去問にのっている粒度の問題です。模試すべての問題の復習はしなくてOKです。
まとめ
勉強法をいくつか紹介しましたが、一番大切なのは購入したテキスト、入学した予備校を信じることです。 そして変えないこと。難しい、、わからないと思っても信じて使い続けてください。 難しすぎて自分は本当に受かるのだろうか。。。?と思うこともたくさんありました。 必ずわかるようになります。勉強すれば誰でも合格する資格です。 あなたの合格を祈っています。
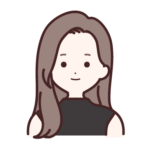
感覚的には一通り流れを把握してから300時間必要でした。 次に宅建試験に合格するための勉強方法を紹介します。
宅建にするための勉強方法
宅建に合格するには「独学」「通信講座」「学校・予備校」の方法があります。 それぞれにあった方法で合格を目指しましょう。
独学
宅建は独学で合格する方も多くいます。
今の時代はありがたいことにYouTubeで宅建の講義を無料で見ることができますが、正直おすすめはできません。 私は独学で受験していた時、YouTubeの画面にかじりついて全編視聴しました。 しかし次の年に学校の教材で勉強すると、知らなかったこと、勘違いで理解していたことがたくさん出てきました。 あくまで個人的な意見ですがYouTubeの動画では下記理由からおすすめできません。
- 大まかな点のポイントだけをつまんで動画にしているので流れが理解しにくく、齟齬が生じやすい
- もともと頭のいい方が作っているため一般人にはわかりにくい
- 動画の流れで理解した気になってしまう
なので、「不動産業についていて質問できる人がいる」「民法の勉強をしていたのでつまづきやすいの権利関係の解説はいらない」方におすすめです!
独学におすすめのテキスト
2回落ちてるだけあっていろんなテキストを試してます(笑)
1.みんなが欲しかった!宅建士〜シリーズ
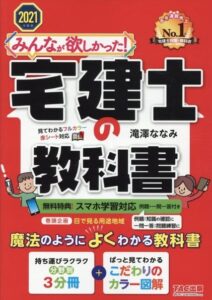
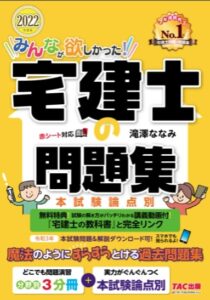 教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
2.LEC 出る順宅建士シリーズ
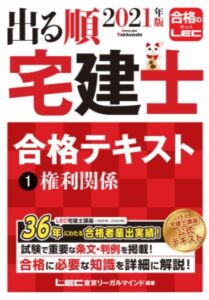
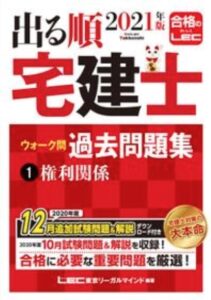 教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
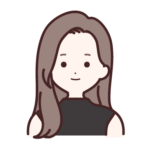
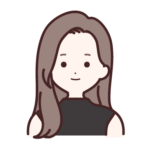
通信講座
正直大手予備校の通信講座以外はおすすめしません。テキストが独特でわかりづらく感じました。私が2回目に勉強したときは独特すぎるテキストについていけず離脱〜
予備校・学校
3回目はついに学校に通いました。(感染症により自宅での映像授業がほとんどでしたが) どうしても受かりたい方はやはり学校がおすすめです。
私は何事も理由と理論がないと暗記できなかったので、理由も一緒に教えてくれる予備校はとてもあっていました。 私はLECに通っていました。やはり法律はLECですね。Twitterの資格アカウントを見ていると行政書士や司法試験もLECを利用している方がダントツで多そうです。 通学でも通信でもいいと思います。 共通しておすすめなのはTwitterの勉強アカウントを作ることです! Twitterで毎日のように勉強報告をしている方のレベルは高いしぼーとTwitterを見てる時に「勉強やらなきゃ」という気持ちになります。何より仲間ができることで途中挫折の確率がぐんと下がります。 すごい人を見て焦燥感や嫉妬で嫌になったりもしますが、辛い気持ちの共有、わかりづらい点、勘違いしていた点の情報共有などメリットがたくさんあります。
おすすめしない勉強法
どうしても言いたいことが2つあります。 一問一答はやりすぎない。 宅建には正解肢だけでなく正解肢以外の解答もチェックする必要があります。 なので一問一答で正解肢だけを覚えていくような勉強はおすすめしません。 もう一つは 模試の復習はやりすぎない。 各会社の模試はとんでもない細かい難しい問題を出してきたりします。しかし宅建に出るような問題は過去問にのっている粒度の問題です。模試すべての問題の復習はしなくてOKです。
まとめ
勉強法をいくつか紹介しましたが、一番大切なのは購入したテキスト、入学した予備校を信じることです。 そして変えないこと。難しい、、わからないと思っても信じて使い続けてください。 難しすぎて自分は本当に受かるのだろうか。。。?と思うこともたくさんありました。 必ずわかるようになります。勉強すれば誰でも合格する資格です。 あなたの合格を祈っています。
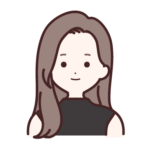
結論!資格学校に甘えるのがおすすめ!
私的には、LECの通信講座or通学講座が一番おすすめ!
\無料会員登録で3000円OFFクーポンもらえる/
独学だと覚えようと勝手に理論を作り上げて余計ごちゃごちゃになりました。 YouTubeで教えている人もいますが、それは頭のいい人が頭いい人向けに説明しているもの。お金はかかりますが素直にプロに教えてもらうのが一番! 他の予備校に通っていた宅建仲間が、宅建合格後LECに通ってました!最初から法律の得意なLECに通っておけばよかった!とのことです。
宅建とは?
宅建や宅建士は「宅地建物取引士」の略称で、毎年20万人前後の受験者数を誇る最大規模の国家資格です。宅建とは、不動産取引の専門家(宅建士)を示す資格です。 宅建士になるための試験を宅建試験といいます。宅建試験に合格すると宅建士として、不動産の売買や賃貸物件のあっせんをする際に、その土地や建物について専門知識を有していないお客様に詳しい説明をすることができるようになります。 不動産の売買や賃貸借の媒介(仲介)といった不動産取引をおこなう場合、従業員5名につき1名以上の宅建士の設置が義務付けられています。 また、不動産に関する重要事項の説明などは宅建士資格を所持していないとできない独占業務です。引用:TAC
宅建がないとできない業務や1つの事務所に必要な数の宅建士の設置義務があるため、不動産業を営む会社で働く人には欠かせない資格です。 また宅建は下記の理由から仕事に関係なく趣味として取得する方も多いようです。
- 誰にでも受験資格がある
- 法律系国家資格の入門
- 4肢択一のマークシート形式
宅建試験はどんな試験?
宅建士の試験は
- 権利関係(14点)
- 宅建業法(20点)
- 法令上の制限(8点)
- 税・その他(8点)
の4科目からなり、この中から全50問出題されます。
権利関係
権利関係は「民法」「借地借家法」「不動産登記法」などから出題されます。 民法特有の考え方や用語が多いので初心者にはとっつき食い科目ですね。
宅建業法
宅建業法は宅建士として必要な知識を問われます。具体的には「賃貸や売買で説明しなければならないこと」「報酬はいくらまで」といった感じです。暗記がほとんどなので時間をかければできます。
法令上の制限
法令上の制限は建物をたてるときのルールを問われます。具体的には「この地域にはこの建物を建ててはならない」「高さ何m以上の建物にはエレベーターを設置しなければならない」などという感じです。こちらも暗記がメインです。
税・その他
相続税や住宅を購入する時に必要な税金の知識が問われます。こちらも暗記がメインです。ただ仕組みが複雑なので理解しながら覚える必要があります。 宅建は難易度は他の国家資格と比べるとやや高めです。
宅建の難易度は?
宅建の合格率はここ10年15~17%前後に推移しています。 具体的には申込者が約25万人、受験者が20万人、合格者が約3.5万人です。 国家資格の中では合格率は高いとは言え、毎年受験生の約17万人が落ちています。 簡単に合格する資格とは言えません。
必要な勉強時間
宅建士に合格するにはだいたい300~400時間ほど必要と言われています。 しかし法律系の勉強をしたことがない方、不動産業務に関わったことがない方はもっと時間が必要だと思います。
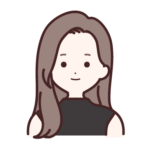
感覚的には一通り流れを把握してから300時間必要でした。 次に宅建試験に合格するための勉強方法を紹介します。
宅建にするための勉強方法
宅建に合格するには「独学」「通信講座」「学校・予備校」の方法があります。 それぞれにあった方法で合格を目指しましょう。
独学
宅建は独学で合格する方も多くいます。
今の時代はありがたいことにYouTubeで宅建の講義を無料で見ることができますが、正直おすすめはできません。 私は独学で受験していた時、YouTubeの画面にかじりついて全編視聴しました。 しかし次の年に学校の教材で勉強すると、知らなかったこと、勘違いで理解していたことがたくさん出てきました。 あくまで個人的な意見ですがYouTubeの動画では下記理由からおすすめできません。
- 大まかな点のポイントだけをつまんで動画にしているので流れが理解しにくく、齟齬が生じやすい
- もともと頭のいい方が作っているため一般人にはわかりにくい
- 動画の流れで理解した気になってしまう
なので、「不動産業についていて質問できる人がいる」「民法の勉強をしていたのでつまづきやすいの権利関係の解説はいらない」方におすすめです!
独学におすすめのテキスト
2回落ちてるだけあっていろんなテキストを試してます(笑)
1.みんなが欲しかった!宅建士〜シリーズ
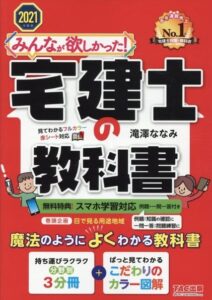
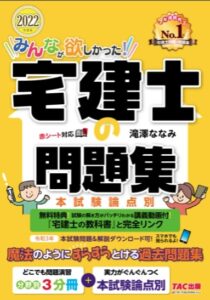 教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
教科書/問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 他の資格でも大人気!みん欲しシリーズ!内容がとてもわかりやすく噛み砕いて書いてあります。初心者から宅建合格した方はこちらで勉強していたとよくTwitterで見かけましたよ♪中身もカラフルで飽きません。 しかし法律系の勉強をしたことがある人や、論文を多く読んだ経験がある人、契約書など長い文章を日頃から読む人には噛み砕かれすぎていて、逆に全体像が見え辛くなっています。 そんな方にはこちら!
2.LEC 出る順宅建士シリーズ
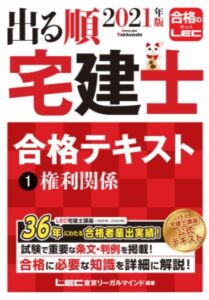
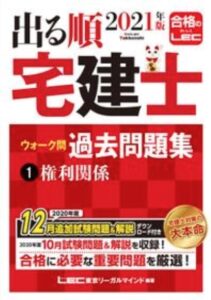 教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
教科書/ウォーク問過去問題集 (リンクは最新の年度の教科書が出るようになってます) 黒、赤、グレーの三色で「カラフルなテキストは頭に入ってこない」「シンプルなテキストが好き」という方におすすめです。 4科目が3冊におさまっています。ボリューミー!!! しかし必要なボリュームです。 やりきった時、達成感が半端ないです。
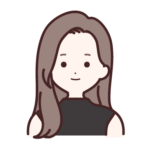
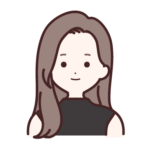
通信講座
正直大手予備校の通信講座以外はおすすめしません。テキストが独特でわかりづらく感じました。私が2回目に勉強したときは独特すぎるテキストについていけず離脱〜
予備校・学校
3回目はついに学校に通いました。(感染症により自宅での映像授業がほとんどでしたが) どうしても受かりたい方はやはり学校がおすすめです。
私は何事も理由と理論がないと暗記できなかったので、理由も一緒に教えてくれる予備校はとてもあっていました。 私はLECに通っていました。やはり法律はLECですね。Twitterの資格アカウントを見ていると行政書士や司法試験もLECを利用している方がダントツで多そうです。 通学でも通信でもいいと思います。 共通しておすすめなのはTwitterの勉強アカウントを作ることです! Twitterで毎日のように勉強報告をしている方のレベルは高いしぼーとTwitterを見てる時に「勉強やらなきゃ」という気持ちになります。何より仲間ができることで途中挫折の確率がぐんと下がります。 すごい人を見て焦燥感や嫉妬で嫌になったりもしますが、辛い気持ちの共有、わかりづらい点、勘違いしていた点の情報共有などメリットがたくさんあります。
おすすめしない勉強法
どうしても言いたいことが2つあります。 一問一答はやりすぎない。 宅建には正解肢だけでなく正解肢以外の解答もチェックする必要があります。 なので一問一答で正解肢だけを覚えていくような勉強はおすすめしません。 もう一つは 模試の復習はやりすぎない。 各会社の模試はとんでもない細かい難しい問題を出してきたりします。しかし宅建に出るような問題は過去問にのっている粒度の問題です。模試すべての問題の復習はしなくてOKです。
まとめ
勉強法をいくつか紹介しましたが、一番大切なのは購入したテキスト、入学した予備校を信じることです。 そして変えないこと。難しい、、わからないと思っても信じて使い続けてください。 難しすぎて自分は本当に受かるのだろうか。。。?と思うこともたくさんありました。 必ずわかるようになります。勉強すれば誰でも合格する資格です。 あなたの合格を祈っています。